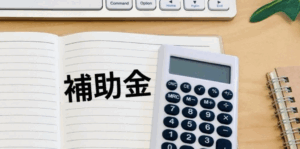コンテナを使った輸送において、積載重量の正確な把握は今や不可欠な時代です。特にSOLAS条約によって、コンテナの重量確認は法的にも義務化されており、違反すれば出荷そのものが拒否される可能性もあります。
安全な輸送を維持し、無駄なコストやトラブルを避けるためにも、信頼性の高い計量が求められています。本記事では、コンテナ重量の計測がなぜ必要なのか、どのような計測方法があるのか、そして最もおすすめの方法や注意点、導入時に押さえるべきポイントについて解説します。ぜひ本記事を最後まで読んで、参考にしてみてください。
また、以下の記事ではメディア厳選のおすすめトラックスケールメーカーを紹介していますので、気になる方はぜひ一度チェックしてみてください。
コンテナ重量の計測は義務化されている!
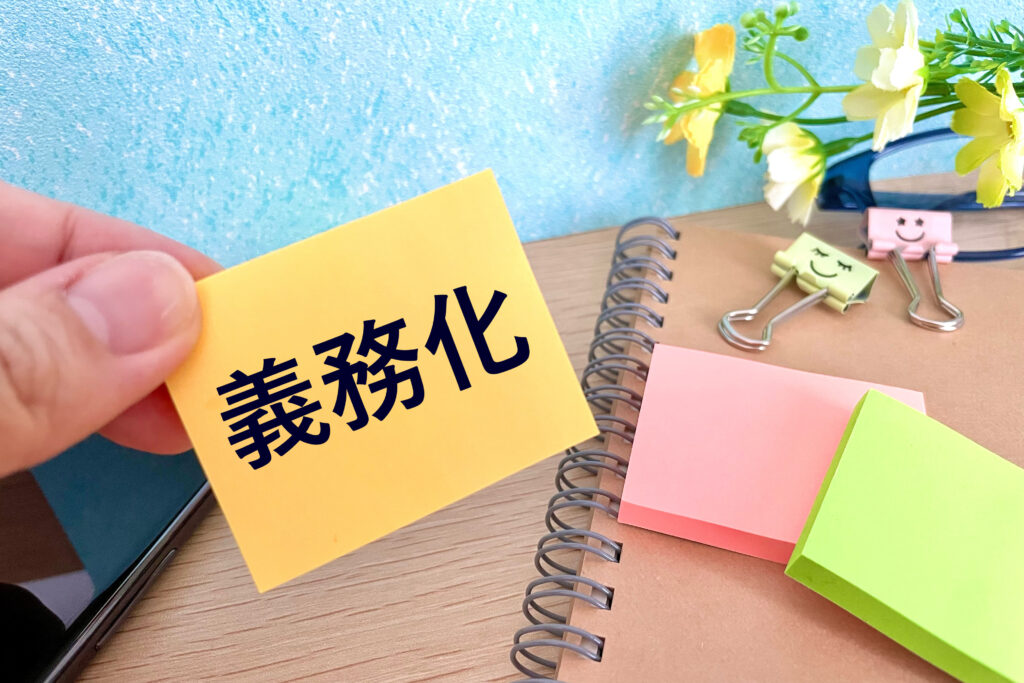
コンテナ重量の計測は、2016年7月に改正施行されたSOLAS条約(海上人命安全条約)により義務化されています。
具体的には、輸出されるすべての海上コンテナについて、出荷前に『VGM=検証された総重量』を船会社に報告しなければなりません。VGMの提出は荷主の責任とされており、報告がなければコンテナが船に積まれない可能性もあります。
この制度は、船舶のバランス崩壊や積載超過による事故を防ぐことが目的であり、国際物流の安全性向上に寄与しています。法令に適合した計量機器の導入と、正確な重量データの管理が、今や輸送業務の基本条件といえるでしょう。
コンテナ重量の計測が必要な理由

コンテナ重量の正確な計測は、単なる法令対応にとどまりません。物流業務全体の安全性や効率性、コスト管理においても重要な役割を果たします。
ここでは、コンテナ重量の計測が必要な主な理由を、3つ紹介します。
これらの観点から、なぜコンテナ重量の計測が必要なのかを以下で詳しく解説します。
輸送の安全性確保
輸送において最も重要なのが、安全性の確保です。コンテナの重量が不明確なままだと、積載超過による車両の横転や荷崩れ、船舶でのバランス崩壊といった重大事故につながるリスクがあります。
特に長距離輸送では、わずかな重量の違いが事故の原因になることもあるため、正確な重量計測は不可欠です。安全な輸送体制を整えるためには、確実に計測されたデータに基づいた積載管理が求められます。
物流コストの最適化
重量を正確に把握することで、物流コストの無駄を省くことができます。なぜなら、積載量の上限を正しく判断することで、車両の配車効率が向上し、輸送回数や燃料費を削減することができるからです。
また、過積載による罰則やメンテナンスコストの増加を防ぐこともでき、長期的な運用コストを最適化する上でも、計測の精度は重要な指標となります。無駄のない物流を実現するためにも、正確な重量管理は欠かせません。
法的規制の遵守
国内外を問わず、物流に関わる法令や規制は年々厳しくなってきています。特に海上輸送では、SOLAS条約に基づくVGMの提出が義務となっており、未提出や虚偽の申告は積載拒否や罰則の対象となります。
さらに国内では、過積載に関する道路交通法や労働安全衛生法など、複数の法規制にも対応する必要があります。これらの法的要件を確実に満たすためにも、信頼性の高い計量機器によるコンテナ重量の管理が不可欠です。
コンテナ重量の計測方法にはどんな種類がある?

コンテナ重量の計測には、用途や現場の設備に応じていくつかの方法が存在します。それぞれに特徴があり、導入目的やコスト、スペースの観点から適した方式を選ぶことが重要です。
ここでは、コンテナ重量の計測方法の種類について解説します。
それぞれの種類について、以下で詳しく解説します。
荷物単体を個別に測定する方法
まず1つ目は、荷物ごとに個別重量を測定し、合算してコンテナ全体の重量を算出する方法です。シンプルな台秤やフロアスケールを用いるケースが一般的で、既存の荷積み作業と並行して行いやすいメリットがあります。
ただし、積載物が多い場合や種類が異なる場合は、作業負荷が増えるうえ、記録ミスや合算ミスのリスクが伴うので注意が必要です。小規模事業者や簡易的な出荷現場などには向いていますが、大量出荷を扱う現場では非効率になることもあります。
クレーンスケールやフォークリフトスケールの活用
2つ目は、荷物を吊り上げるタイミングで重量を測定できる『クレーンスケール』や『フォークリフトスケール』を活用する方法です。
荷役作業と同時に計量できるため、作業効率が高く、移動を最小限に抑えられるのが大きな特長です。特に大型機器やバラ積み品の取扱い現場では有効ですが、正確な計測には一定の熟練やメンテナンスが必要です。
また、機器の導入コストや定期点検のコストが発生する点も考慮する必要があります。
トラックスケールで一括測定する方法
3つ目は、『トラックスケール』を活用して一括測定する方法です。トラックスケールは、コンテナを積載したトラックごと台貫に載せ、車両総重量から空車重量を差し引いてコンテナ重量を算出することができます。
測定精度が高く、積載状態をそのまま測れるため、出荷直前での確実な重量把握が可能です。SOLAS条約に対応する正式なVGM計量にも適しており、最も信頼性の高い方法のひとつとされています。
設置にはスペースとコストがかかりますが、中〜大規模事業者にとっては業務効率と法令対応の両立が図れる手段です。
コンテナ重量の計測で最もおすすめなのは『トラックスケール』

コンテナ重量の計測方法として最もおすすめなのが『トラックスケール』の導入です。トラックスケールは、コンテナを積載したトラックごと計量できるため、積み込み後の状態をそのまま正確に把握することができます。
作業の流れを妨げずに高精度な重量管理が可能で、VGMの報告にも対応できる信頼性の高い方法です。特に、出荷量が多い現場や法令遵守が求められる国際輸送では、その実用性と効率性が大きな強みとなります。
設置コストはかかりますが、長期的にはミスの削減や業務の最適化にもつながる有効な投資といえるでしょう。
コンテナ重量の計測でトラックスケールがおすすめな理由

ここでは、コンテナ重量の計測でトラックスケールがおすすめな理由について、さらに詳しく解説します。
以下でそれぞれの特長について、より詳しく解説します。
コンテナを積載した状態で丸ごと測定できる
トラックスケールの最大の強みは、コンテナを積載したまま一括で計量できる点にあります。荷降ろしや個別測定を行う必要がなく、車両ごと計量台に乗せるだけで、積載状態のまま正確な重量を把握できます。
この方法は時間と手間を大きく削減できるため、現場の負担を軽減し、出荷前の業務フローにもスムーズに組み込むことが可能です。
また、積載状態そのままの計測は、実運用に即した数値を得られるため、誤差の少ない安全な物流管理にも直結します。
SOLAS条約にも確実に対応できる
トラックスケールは、海上輸送において義務付けられているSOLAS条約のVGM要件にも適合しています。計量法に基づいた検定済みのトラックスケールであれば、法的にも信頼できる計測方法として正式に認められています。
個別に計算した重量ではなく、車両全体の実測値で報告ができるため、計測ミスのリスクも最小限に抑えることが可能です。国際輸送を行う事業者にとっては、安心して法令遵守ができる設備として大きなメリットとなるでしょう。
大型車両の計測にも対応可能で、設備として信頼性が高い
トラックスケールは、大型トレーラーやコンテナシャーシなど、長さや重量のある車両にも対応できる仕様で設計されています。計量精度の高さはもちろん、車両の長さに合わせた設置も可能なため、柔軟な現場対応が可能です。
また、多くのトラックスケールは屋外設置を前提に作られており、耐久性や保守性の面でも高い信頼性を誇ります。法令対応とあわせて、長期間安心して使える設備として、多くの物流拠点で採用されています。
コンテナ重量における計量機器を導入する際の注意点

コンテナ重量の計測は法令対応や業務効率の観点からも非常に重要ですが、計量機器を導入する際は事前に押さえておくべき注意点がいくつかあります。
せっかく機器を導入しても、仕様や設置環境が合っていなければ期待した効果が得られないこともあります。長期的に安定した運用を実現するためには、以下のポイントを事前にチェックすることが不可欠です。
以下でそれぞれの注意点について、詳しく解説します。
法令対応済みの機器かを確認すること
コンテナ重量の正確な計測には、計量法に基づいた検定済みの機器を使用することが基本です。特にSOLAS条約に基づくVGMの報告では、法令に適合した計量機器であることが前提条件となります。
検定に合格していない機器を使用すると、誤った重量データによる報告となり、コンプライアンス違反につながる可能性もあるので注意が必要です。購入・導入前には『検定ラベルの有無』『VGM対応証明』『計量証明書の発行可否』などを必ず確認しましょう。
設置環境と機器の相性を見極めること
導入する計量機器が現場の設備や動線に適していなければ、運用上のトラブルや非効率の原因となります。たとえばトラックスケールであれば、十分な設置スペースや通過経路、排水環境が整っているかを事前に確認する必要があります。
クレーンスケールやフォークリフトスケールであっても、既存の機材との互換性や重量制限などとの相性確認が不可欠です。現場と運用フローをよく理解したうえで、適した機器を選定することが失敗を防ぐカギとなるでしょう。
記録・出力機能が自社システムと連携できるか確認する
近年では、計量データを印字やデジタル出力し、帳票や在庫管理システムへ連携させるニーズが増えています。そのため、導入を検討している機器に『伝票印字機能』『USB/LAN出力』『クラウド連携』などの記録機能があるかどうかも重要なチェックポイントです。
VGMの報告書出力や、出荷履歴の保存・管理を効率化できる機能があれば、業務全体の精度と効率が格段に向上します。システム連携を前提とした導入計画を立てることが、将来的な拡張性にもつながるでしょう。
コンテナ重量における計量機器導入を成功させるためのポイント

計量機器の導入は、単に機械を設置すれば完了というわけではありません。現場の運用に定着させ、確実な成果を出すには、導入の段階から準備すべきポイントがあります。
現場環境の確認や目的の整理、パートナー選びを丁寧に行うことで、無駄なトラブルや再投資を防ぎ、導入効果を最大化できるでしょう。
ここからは、コンテナ重量における計量機器導入を成功させるためのポイントについて解説します。
以下でそれぞれのポイントについて、詳しく解説します。
現場に合った機器の選定を行う
計量機器は現場環境や運用フローに応じて適切な機種を選定する必要があります。たとえばトラックスケールは、大型車両の一括計量に向いている一方、設置スペースや車両動線の確保が不可欠です。
フォークリフトスケールやクレーンスケールは省スペースで導入しやすい反面、操作には一定の習熟が求められます。したがって、現場の物理的制約・作業手順・作業者スキルなどを総合的に考慮し、最適な機器を選定することが大切です。
導入目的を社内で明確にしておく
計量機器の導入効果を最大限に活かすには、なぜ導入するのかという目的を社内で共有しておくことが不可欠です。なぜなら、目的が曖昧なままだと、現場の理解が得られず、機器が使われなくなったり、運用が定着しない原因となるからです。
たとえば『VGM対応のため』『過積載防止』『原価管理の強化』など、導入の背景と達成すべき課題を具体的に明示することが大切です。社内説明会や運用マニュアルを通じて、関係者の認識をそろえることが成功への第一歩となるでしょう。
信頼できる計量機器メーカーを選ぶ
機器そのものの性能だけでなく、導入後のサポートやトラブル対応も含めて信頼できるメーカーを選ぶことが、安定した運用につながります。特にトラックスケールなどの大型設備では、設置・初期設定・校正・修理・保守点検まで一貫対応してくれる企業を選ぶと安心です。
国内に拠点があるか、導入実績が豊富か、法令対応や検定サポートが受けられるかなども重要な評価軸です。長く付き合えるパートナーとしての視点で、信頼性を重視して選定しましょう。
信頼できる計量機器メーカーの選び方

計量機器は長く使い続ける設備であり、導入後も安定した精度や運用を維持するには、信頼できるメーカーを選ぶことが極めて重要です。
初期費用や見た目のスペックだけで判断するのではなく、法令対応やアフターサポート、導入実績といった観点から総合的に比較・検討することが、失敗しないメーカー選びのポイントになります。
ここからは、信頼できる計量機器メーカーの選び方について解説します。
それぞれの項目について、以下で詳しく解説します。
法令対応や検定実績があるかを確認する
VGMやトラックスケールなど、コンテナ重量の正確な測定を行うには、計量法に適合した機器であることが前提条件です。特に法令遵守が求められる業務では、検定付き機器の使用が義務化されている場合もあります。
信頼できるメーカーであれば、計量法の検定実績が豊富で、必要に応じた証明書の発行や認定支援もスムーズに対応してくれます。導入前には『検定対応モデルか』『VGM提出に使用できるか』を明確に確認し、法令に基づいた安心の機器選びを行いましょう。
導入から保守まで一貫対応できる体制があるか
計量機器は導入後も定期的な点検や保守、トラブル対応が必要となるため、メーカーがどこまで一貫して対応してくれるかが重要な判断基準になります。
なぜなら、据付工事・設置調整・初期設定・操作説明・定期校正・不具合時の対応まで一括で行ってくれるメーカーであれば、外注や複数業者の連携に頼る必要がなく、トラブル時も迅速かつ確実に対応してもらえるからです。
安定した長期運用を実現するためにも、総合対応力を持つメーカーを選ぶことが大切です。
サポート体制が整っているか
計量機器は、運用中にトラブルや仕様変更への対応が求められる場面が必ず出てきます。そうした時に、すぐに連絡が取れて、技術的な質問にも的確に対応してくれるメーカーであれば、安心して長く使用することができます。
特にトラックスケールのような屋外設備では、急な不具合や気候による不調への対応力が問われます。電話・メール・訪問など柔軟なサポート体制が整っているか、そして地域拠点があるかどうかも事前に確認しておくと安心です。
トラックスケールの導入を検討している方におすすめの会社2選

トラックスケールは高額な設備投資であると同時に、日常の計量業務の精度と効率を左右する重要な装置です。そのため、メーカー選びは製品スペックだけでなく、サポート体制や現場対応力までを含めて慎重に判断する必要があります。
ここでは、実績・品質・保守対応のいずれにも定評がある信頼性の高い計量機器メーカーを2社ご紹介します。
それぞれの特徴について以下で詳しく解説します。
宝計機製作所

宝計機製作所は、計量機器専門メーカーとして全国に導入実績を持つ企業であり、トラックスケールの分野でも高精度かつ高耐久な製品を提供しています。
| 項目 | 詳細 |
| 会社名 | 株式会社宝計機製作所 |
| 所在地 | 山口県柳井市柳井3889番地 |
| 創業 | 昭和25年1月 |
| 電話番号 | 0820-22-0389 |
| 公式サイト | https://www.takara-scale.co.jp/index.html |
トラックスケールをはじめ、デジタルスケールや液体・粉体充填装置、選果システム、防爆システム機器など、産業用途に合わせた多彩な製品ラインナップを展開。なかでもトラックスケールは、信頼性の高い重量計測と安定した運用を支える構造設計により、物流や製造業における計量作業の効率化に大きく貢献しています。
また、ソフトウェアやデータ収集システムとの連携にも対応しており、IoT時代に即したスマート計量管理も可能です。高精度かつ現場目線に立った製品を求める企業におすすめの計量機メーカーです。
また、以下の記事では株式会社宝計機製作所に付いて紹介しているので参考にしてください。

クボタ

クボタは、農業機械や水環境機器で知られる総合メーカーですが、計量機器分野においても長年の実績を持つ企業です。
| 項目 | 詳細 |
| 会社名 | 株式会社クボタ |
| 所在地 | 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー20階 |
| 創業年数 | 1924年 |
| 電話番号 | 03-3245-3915 |
| 公式サイト | https://scale.kubota.co.jp/ |
トラックスケールにおいては、精度・堅牢性・使いやすさを兼ね備えた設計が特長で、国内の物流・建設・製造現場を中心に多数の導入実績があります。自社一貫体制による設計・製造・保守対応が可能なため、トラブル発生時のスピード対応や定期メンテナンスも安心です。
また、全国に支店や営業所があるため、地域に根ざした迅速な対応が受けられる点も大きな魅力のひとつです。
以下の記事では株式会社クボタの会社の特徴や製品事例をさらに詳しく解説していますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。

まとめ
本記事では、コンテナ重量の計測が義務化された背景や、正確な計量がなぜ必要なのか、具体的な計測方法とその選び方、さらに導入時の注意点や成功のポイントまでを解説しました。
特におすすめの計測手段として紹介したトラックスケールは、信頼性・効率性・法令対応の面で優れており、多くの現場で活用されています。計量機器の導入は一度きりの選定ではなく、長期運用を見据えたパートナー選びが重要です。
今後の輸送品質の向上とコスト管理の最適化に向けて、本記事を参考に、最適な導入・運用を進めてみてください。