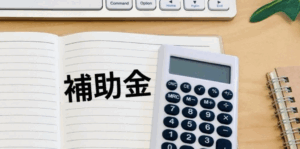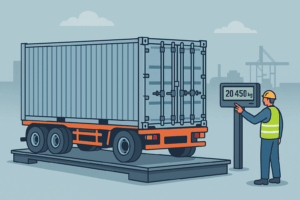トラックの過積載とは、積載量を超えてしまうことを指します。過積載は重大な交通事故や車両の損傷、法的な罰則につながるリスクをはらんでいます。
そのため、過積載の基準や危険性、罰則を理解し、適切な対策を講じることが必要です。これによって事故の未然防止や罰則回避につながるだけでなく、車両の寿命延長や燃費改善などのメリットも得られます。
さらに、従業員の安全確保や企業としての信頼性向上にも寄与するでしょう。本記事では、過積載の概要から事故の危険性、罰則内容、現場で実践できる防止策までを徹底解説します。ぜひ最後までご覧ください。
また、以下ではおすすめの組み合わせはかりメーカーについて紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
トラックの過積載とは?

過積載とは、トラックに積載できる最大重量を超えて荷物を載せてしまう行為を指します。車両には「最大積載量」が法律で定められており、それを上回る積載は道路交通法に違反していることになります。
過積載違反は、走行中の制動距離が伸びたり、タイヤやブレーキに過剰な負担がかかったりするため、重大な事故につながる危険があります。特に高速道路や下り坂などでは、過積載車両の制御が難しくなり、多重事故の引き金になり得るでしょう。
そのため、過積載は運転手自身の安全や周囲の交通に対する、重大な脅威といえます。
過積載が起こってしまう背景
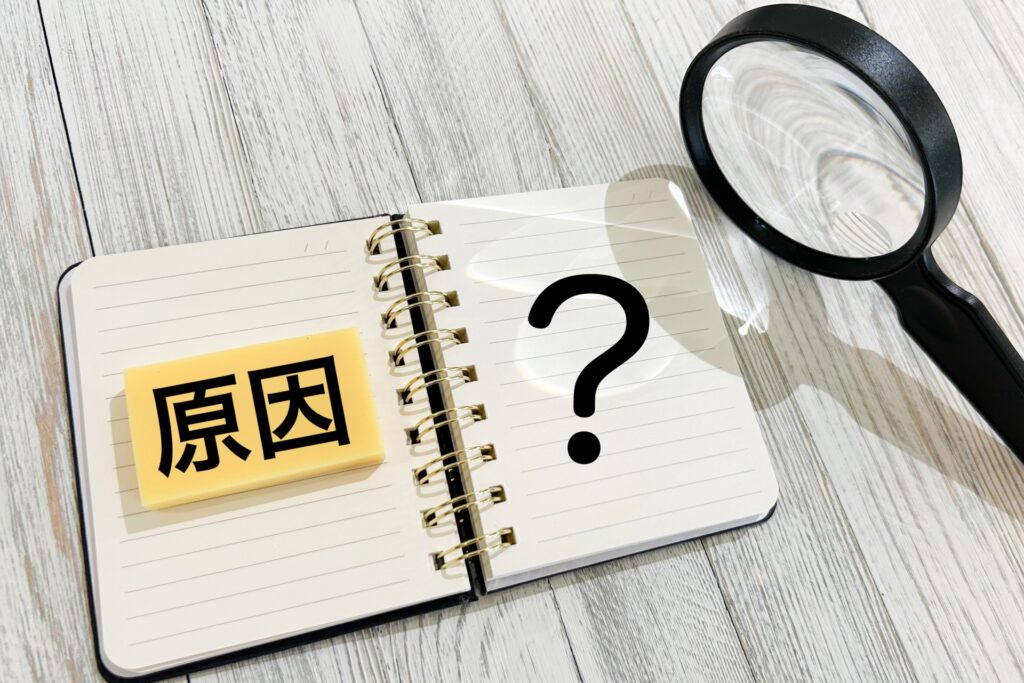
過積載が発生してしまう背景には、以下の要因が想定されます。
- 一度に多く運びたいというドライバーの心理
- 積載量を把握する設備が整っていない
- 荷主からの積載指示
代表的なものは、配送スケジュールの厳しさやコスト削減のプレッシャーです。限られた人員と時間で荷物を運ぶ必要がある現場では、「1回で多く運んだ方が早い」という意識が働きやすくなります。
また、積載量を把握するための設備が整っていない事業所も少なくありません。小規模な運送業者では、計量器やトラックスケールが導入されていないケースが多く、経験や目視に頼った積載判断になりがちです。
さらに、荷主からの積載指示に逆らいにくいという点も過積載の要因です。「多少オーバーしても大丈夫」といった認識が現場に根付いてしまうと、過積載が常態化する恐れがあります。
過積載の責任の所在は誰にある?

トラックの過積載が発覚した場合、運転手だけが罰せられると思われがちですが、実際には関係者それぞれに法的責任が課される可能性があります。
道路交通法や貨物自動車運送事業法では、過積載を防止する責任が運転手だけでなく、運送事業者や荷主にも及ぶことが明記されています。以下では、それぞれの立場における責任について解説していきます。
トラックのドライバー

過積載に最も関与しているのがドライバーです。ドライバーには運転前に積載量を確認し、過積載でないかを見極める義務があります。
たとえ荷主や会社の指示であっても、違法な積載を知りながら運行した場合、道路交通法違反により罰則の対象となります。具体的には、過積載の程度に応じて反則金や違反点数の加算が科され、悪質なケースでは免許停止や罰金刑に至るでしょう。
ただし、ドライバーが独自に重量を確認する手段がない場合もあり、現場の実情を考慮したサポート体制も重要です。運転手個人に過度な責任が集中しないよう、企業全体として対策を講じる必要があります。
運送事業者
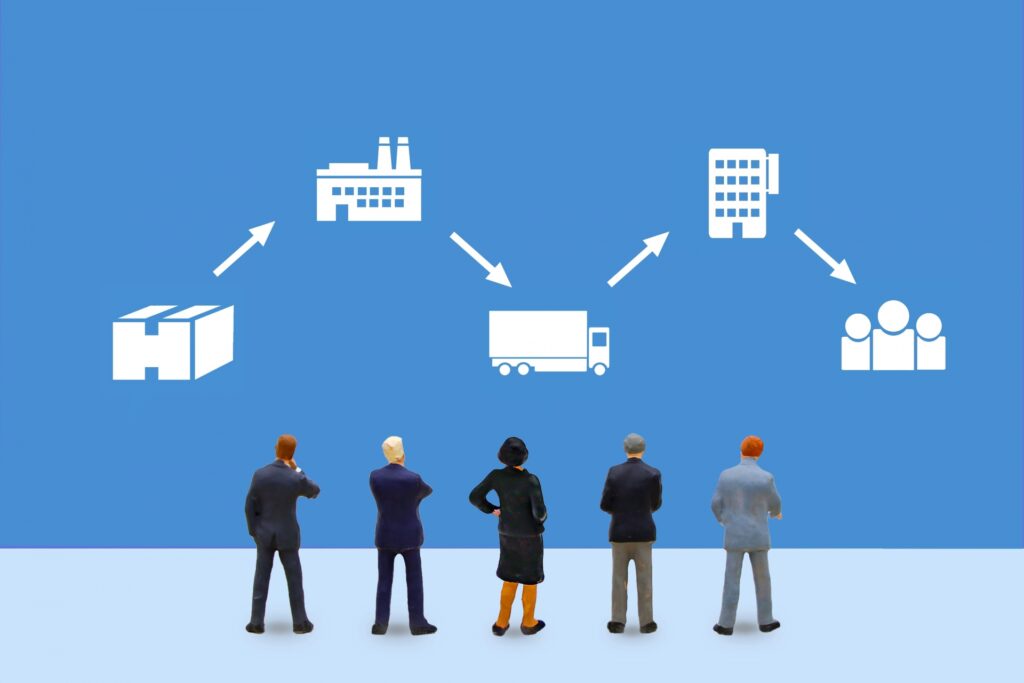
運送会社には、適正な輸送体制を整備する義務があります。点呼時の指導や、車両の積載管理、運転手への教育が不十分であった場合には、事業者としての責任が問われます。
過積載を黙認・指示していたことが判明すれば、監督者や経営層も行政処分の対象となり、最悪の場合は事業停止や営業許可が取り消されるでしょう。
また、運送事業者には貨物の安全輸送に関する管理責任があり、過積載を未然に防ぐための設備投資やマニュアル整備が求められます。計量機器の導入やドライバーへの研修制度の強化は、過積載対策として必須です。
荷主

近年、荷主も過積載に関与しているとされるケースが増えています。改正貨物自動車運送事業法では、荷主にも過積載の防止義務が明記されており、違法な積載を強要した場合には、行政指導や社名公表といった制裁措置が科される可能性があります。
つまり、「荷主の指示だから従った」という言い訳は通用しなくなってきているのです。
荷主としても、積載量を超える発注を避けることや、現場での積み込み管理を徹底することが重要です。過積載のリスクを共有し、物流全体で安全運行を意識した取り組みが求められています。
過積載による事故が起こる危険性

トラックの過積載は、法令違反にとどまらず、重大な事故を引き起こす要因になります。車両の性能は定められた積載量を基準に設計されており、それを超過することで事故リスクを高めます。
過積載によって想定される危険・リスクは、以下の通りです。
それぞれについて解説していきます。
制動距離の増加

過積載状態のトラックは、車両全体の重量が増すため、ブレーキを踏んでから停止するまでに必要な距離(制動距離)が長くなります。これは、ブレーキシステムにかかる負担が大きくなり、本来の性能を十分に発揮できなくなるためです。
このような状況では、前方車両の急停止や障害物に対応が間に合わず、追突事故につながるリスクが高まります。また、制動時にタイヤがロックしたり、車体が横滑りを起こす可能性もあり、ドライバーの操作だけでは回避が困難な場面も増えるでしょう。
タイヤのバースト・車両破損

過積載によってトラックに過剰な荷重がかかると、最も大きな負担を受けるのがタイヤです。想定以上の重量を支えることでタイヤの空気圧が異常に高まり、走行中にバースト(破裂)を引き起こす危険性が高くなります。
タイヤがバーストすると車両の制御が困難となり、高速道路やカーブなどでは致命的な事故を引き起こしやすくなります。また、車両本体にも深刻なダメージを与える点に注意が必要です。
過積載はサスペンションやフレーム、ブレーキなどの構造部品にも負担をかけ、ひび割れや変形、破損を引き起こす原因となります。これにより走行性能が低下し、トラックの寿命を大幅に縮めてしまう可能性があります。
ハンドリング性能の低下

過積載はトラックの重心や荷重バランスを大きく変化させるため、ハンドリング性能に悪影響を与えます。カーブの進入時や車線変更の際に、車両の応答性が鈍くなり、ドライバーの操作に対する反応が遅れるようになります。このような状態では、緊急回避や障害物の回避が難しくなり、追突や接触事故を招く危険性が高まるでしょう。
また、ステアリング操作に必要な力も増大するため、長時間の運転では疲労が蓄積しやすくなります。過積載により足回りの性能が低下すると、通常の走行でも横滑りやふらつきが生じることがあり、悪天候時にはその影響がさらに大きくなるでしょう。
特に都市部や山間部など、急カーブや狭い道路が多い地域では、過積載によるハンドリング性能の低下は致命的です。
車体が傾きやすくなる

過積載によりトラックの荷重バランスが崩れると、走行中に車体が左右どちらかに傾きやすくなります。特にカーブや交差点では遠心力が加わるため、不安定な状態のまま曲がると横転事故につながるリスクが大きくなります。
また、積み荷の配置が偏っている場合、片側にだけ大きな重さがかかることでさらに傾きやすくなるでしょう。車体が傾くことでドライバーの視界にも悪影響が出るため、ハンドル操作が遅れたり、車線を逸脱したりといった二次的な事故につながる可能性も高まります。
荷台の固定が不十分な場合は、傾きをきっかけに積み荷が崩落し、他車両や歩行者を巻き込むおそれもあります。
作業者への負担増加

過積載は運転時のリスクだけでなく、荷物の積み下ろし作業を担う現場作業者にも深刻な負担を与えます。通常よりも重くなった貨物を人力で取り扱う場面が増えると、腰や肩、膝などへの物理的負担が増し、労災につながります。
また、荷台に積み上げられた大量の貨物を限られたスペースで扱うことは、荷崩れや転倒のリスクを高め、作業者の安全を脅かすでしょう。特に荷物が不安定に積まれている場合には、開扉時の落下や衝突といった事故も想定されます。
さらに、過積載は作業時間の長期化や疲労の蓄積を招くため、注意力や集中力が低下し、ヒューマンエラーの誘発にもつながります。
過積載が発覚した場合の罰則

トラックで過積載が行われていることが発覚した場合、関係者にはそれぞれ法的な罰則が科されます。過積載は交通事故の重大な原因にもなり得る行為であるため、道路交通法や貨物自動車運送事業法などに基づき厳しく取り締まられています。
過積載が発覚した場合、以下の関係者の責任・罰則が問われます。
それぞれに対する罰則内容について解説していきます。
ドライバーへの罰則

ドライバーは直接的な関与があるため、過積載車両を運転した場合、その責任は明確に問われます。具体的には、過積載の程度に応じて反則点数と反則金が科され、最大で6点の違反点数が付与されることがあります。
違反点数の累積により免許停止処分となるケースもあり、業務への影響も少なくないでしょう。
また、過積載が悪質と判断された場合には、道路交通法違反として刑事罰の対象となり、罰金や懲役刑が科される可能性もあります。ドライバーによる過積載の責任は非常に重く、「知らなかった」では済まされません。
運送事業者への罰則

過積載を容認・指示した運送事業者には、行政処分が科される場合があります。例えば、運輸局による監査の結果、指導・警告にとどまらず、業務停止命令や営業許可の取消といった厳しい処分を受けることもあるでしょう。
過去に同様の違反歴がある場合や、複数回にわたって過積載を繰り返していた場合は、処分の内容も重くなります。
それだけでなく、社名の公表や社会的信用の失墜により、荷主との契約解消や新規案件の受注停止といった経営リスクもあります。こうした影響は、事業運営としてもリスクがあるといえるでしょう。
荷主への罰則

2019年の貨物自動車運送事業法の改正により、荷主が過積載を強要した場合にも行政指導や社名公表といった処分が下されるようになりました。これは、荷主が法令違反の一因と認定された場合に適用され、運送現場全体での責任共有が求められるようになった証です。
具体的には、過積載を前提とした以下のようなものが対象となり、これらが運送業者に過積載を強いる要因と判断されると処分の対象となります。
- 納品スケジュール
- 数量指定
- 無理な納期要求
そのため、荷主も法令遵守を徹底し、適正な物流管理を行うことが重要です。全てドライバーや事業者の責任とされなくなった点には、注意しなければいけません。
過積載による事故を防止するのに有効な対策
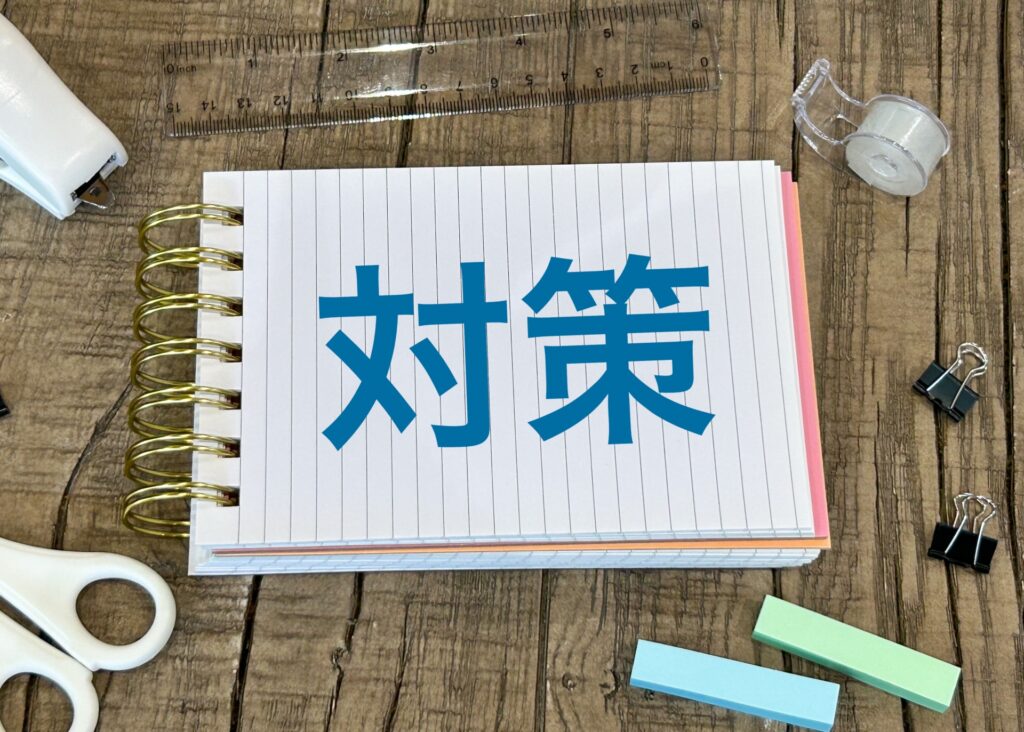
過積載は重大事故や車両トラブルのリスクを高めるだけでなく、関係者に罰則が及ぶ深刻な違反行為です。そのため、未然に防ぐための仕組みづくりと意識向上が欠かせません。
現場で実践できる具体的な対策としては、以下の5つが有効です。
これらの対策を取り入れることで、安全性の向上と法令遵守の徹底が図れます。それぞれの対策について解説していきます。
車両総重量と最大積載量を把握しておく

過積載を防止するための基本は、各車両の「車両総重量」と「最大積載量」を把握することです。これらの数値は車検証に明記されています。特に、車種や仕様ごとに積載可能な重量は異なるため、経験や目視に頼った判断では、正確な積載管理が困難です。
また、荷物の種類や個数だけで重量を見積もると誤差が生じやすく、知らぬ間に過積載になってしまうリスクがあります。そのため、積み込み前に荷物の総重量を確認し、トラックの最大積載量と照らし合わせることが重要です。こうした事前確認の習慣化が、運行中のトラブルや法令違反を防ぐ効果を発揮します。
積載量の把握はドライバー個人に任せるのではなく、社内全体で情報を共有し、組織として積載基準を徹底することで、過積載対策として効果が期待できるでしょう。
デジタコ・運行管理システムの導入
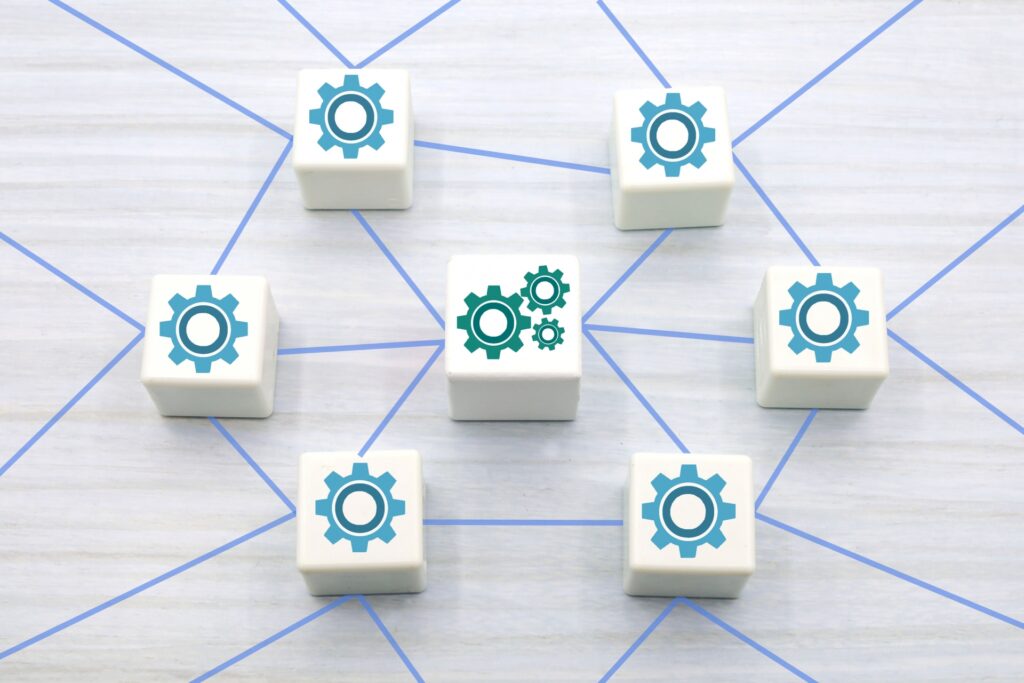
過積載を未然に防ぐための対策として、デジタコや運行管理システムの導入が有効です。これらの機器は、以下の運転挙動を自動的に記録し、リアルタイムで管理者と共有を可能にします。
- 車両の走行速度
- 運転時間
- 急加速・急ブレーキ
デジタコのデータをもとにすれば、ブレーキ温度の上昇や制動距離の変化など、過積載による負荷の増大を早期に把握できます。また、運行管理システムと連携することで、積載量や車両ごとの稼働状況を可視化し、積載オーバーが発生しないよう調整することも可能です。
システム導入によって、現場任せにせず組織的に安全対策を実施できる体制が整うため、過積載の再発防止にもつながります。初期費用はかかりますが、長期的には事故防止・業務効率化という大きな効果が期待できるでしょう。
ドライバー教育・法令周知

過積載による事故を防止するには、ドライバーの意識向上が欠かせません。現場で直接荷物を扱い、運転を担うドライバーが過積載のリスクを理解していなければ、法令遵守や安全運転は実現できません。
まずは、過積載の定義や罰則について研修などを通じて周知を図りましょう。その上で、過去の事故事例を紹介することも、危機意識を高める有効な手段です。実際に起きた過積載による事故の影響や、ドライバーが受けた処分などを共有することで、法令を意識した行動がとれるようになります。
新人や若年層のドライバーに対しては、座学だけでなく、現場での実践を交えた教育を行うことで理解が深まります。会社全体で意識を共有するためにも、教育体制を強化するようにしましょう。
荷主との適正取引を確立させる

過積載は、荷主からの過剰な積載依頼や無理な納期指示によって引き起こされるケースも想定されます。そのため、荷主との間で適正な取引関係を構築し、法令を順守した運送体制を整えることが、事故防止のために不可欠です。
会社側としては、積載基準や車両の最大積載量を荷主側に説明するといった対策が有効です。その上で、荷物の量や配送スケジュールについてすり合わせを行い、無理のない運行計画を共有することで、過積載の抑止につながります。
また、国土交通省が推進する「荷主勧告制度」では、荷主に起因する過積載が確認された場合、勧告や社名公表といった行政対応が行われることもあり、荷主側にも法令順守が求められています。運送事業者としては、必要に応じてこうした制度を活用しながら、安全を最優先にした取引関係を築くことが重要です。
トラックスケールの活用

トラックスケールとは、車両の総重量や積載重量を測定できる装置です。トラックスケールを活用することで、出発前に荷物の重さを数値で確認できるため、過積載かどうかを即座に判断できます。
経験や目視だけに頼る積載判断では誤差が生じやすく、知らぬ間に法令違反となってしまうケースも少なくありません。この点、トラックスケールを使用すれば、客観的に重量を把握できるため、過積載のリスクを大幅に軽減できます。
また、記録を残しておくことで、後々のトラブルや監査時の証拠としても活用できます。簡易型のポータブルタイプであれば、小規模な事業所でも導入しやすいでしょう。
トラックスケールの導入におすすめの会社2選

過積載の防止に活用するトラックスケールを選ぶには、精度・耐久性・サポート体制に優れ、運送現場での信頼性が高いメーカーの製品を選ぶのがポイントです。以下では、トラックスケールの導入におすすめのメーカー2社を紹介します。
それぞれについて解説していきます。
宝計機製作所

宝計機製作所は、山口県柳井市に拠点を置く計量・計測機器の総合メーカーで、トラックスケールを含む多彩な計量システムを自社設計・製造しています。
| 項目 | 詳細 |
| 会社名 | 株式会社宝計機製作所 |
| 所在地 | 山口県柳井市柳井3889番地 |
| 創業 | 昭和25年1月 |
| 電話番号 | 0820-22-0389 |
| 公式サイト | https://www.takara-scale.co.jp/index.html |